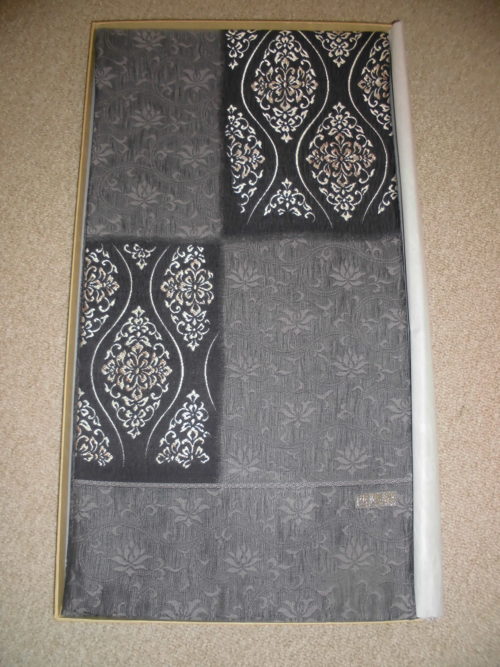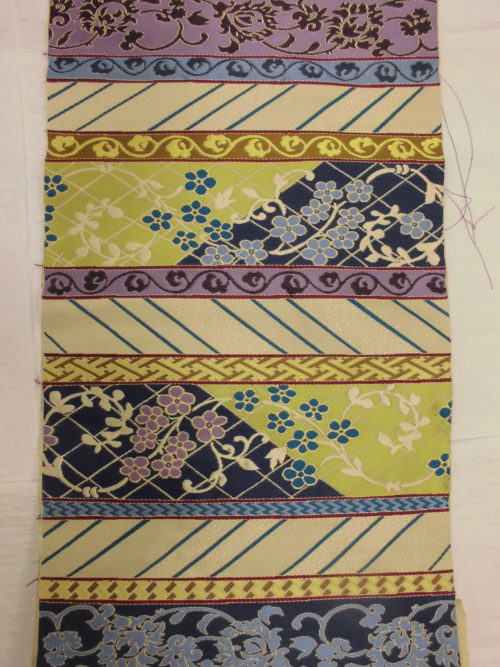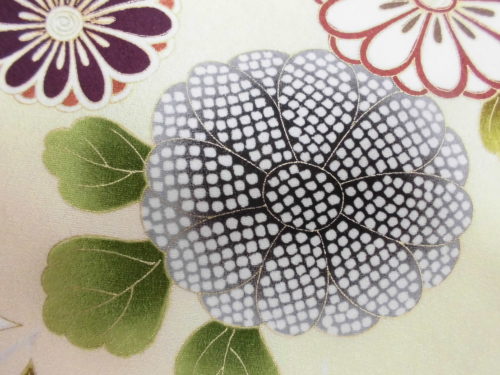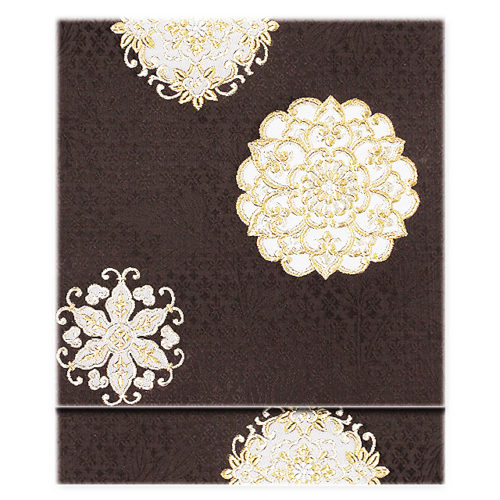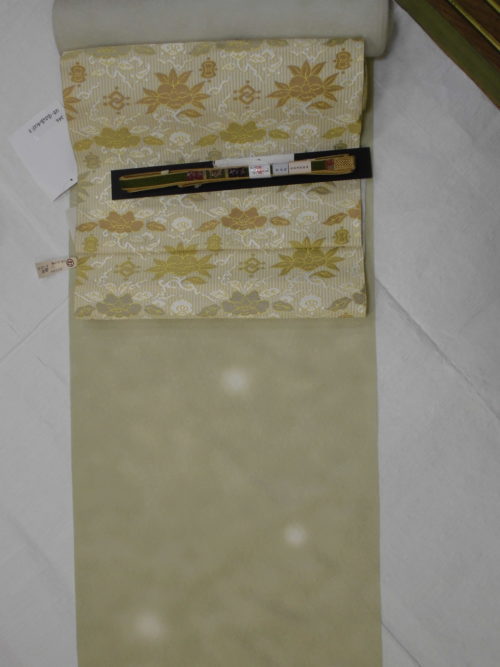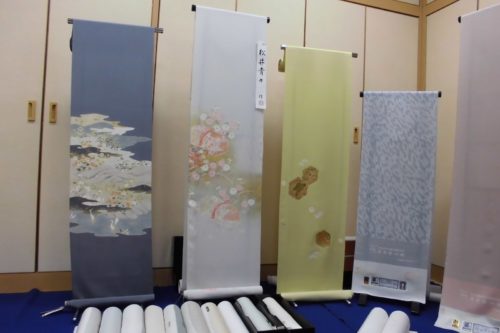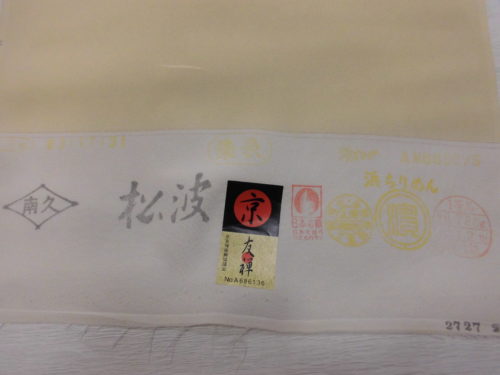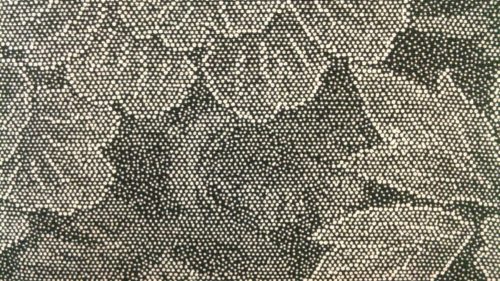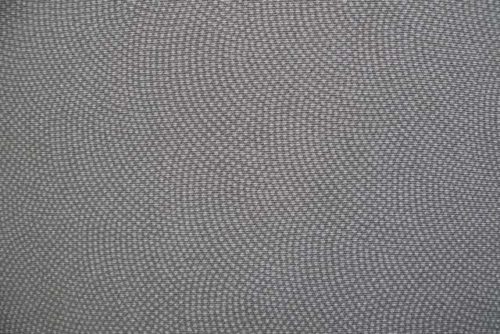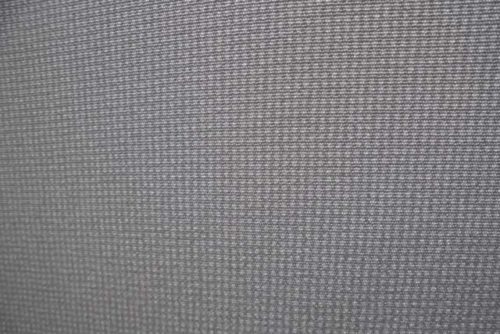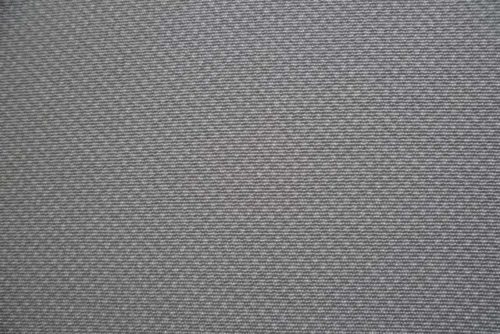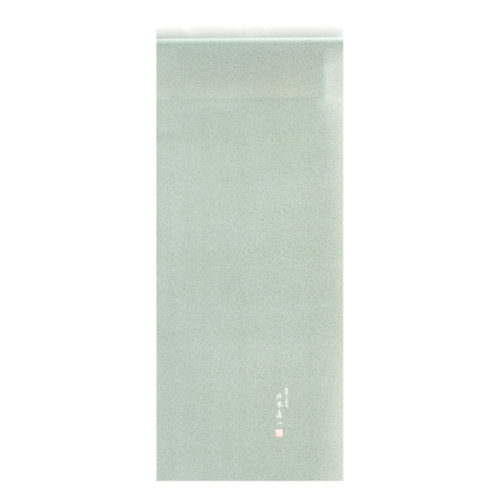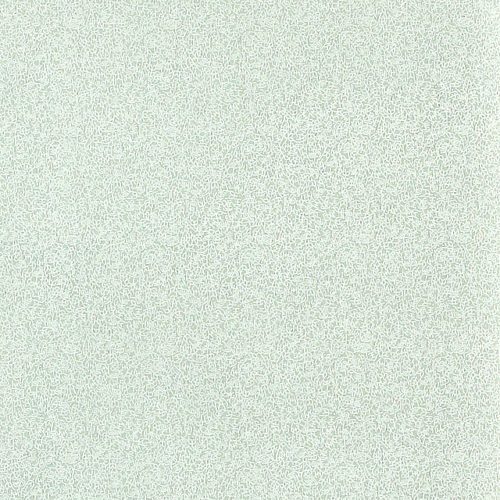帯の仕立てが戻ってまいりました。



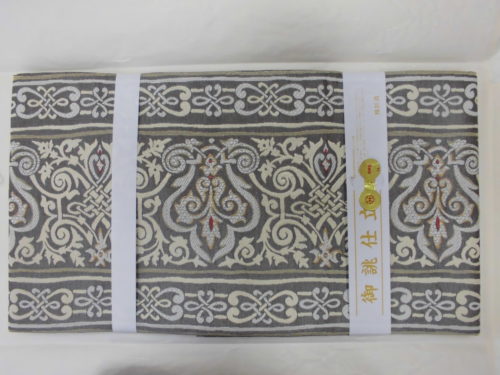

一つ一つたとう紙に入れお納めできる準備をしました。
どのお品もですが、お仕立て前の段階とお仕立て後ですとはるかに仕立て
た後の方がよく見えます。
西陣まいづる・小森の帯・本袋帯・八寸名古屋帯
写真は載せていませんが、弥栄織物さんのなごや帯・いづくら・洛陽織物
等々でした。
3月始めの急ぎの小紋の注文もお仕立てから戻ってまいりました。


シワにならないように美装紙を入れます。
この紙は、当分の間は着物に挟んでおいてもかまいませんが、そのままで
年数が経つのならば、湿気を含んだら取り外してください。
きものが、またその湿気を吸ってカビの原因になります。

衿フトンを置きお袖がしわにならないようにします。
お召しになられて、しまう時は、必ず置いてください。シワ予防です。

きもの枕です。たとう紙に入る大きさに折ると折り目がシワになり易いため
挟みます。

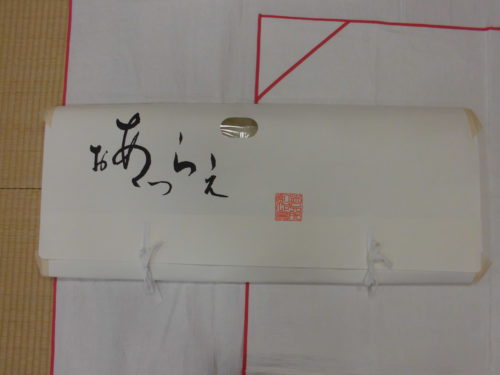
後、検針をして完了です。
弊社の簡単な流れです。
新柄の付け下げ、白綾苑大庭のなごや帯です。白綾苑大庭の名古屋帯は
めずらしいのではないでしょうか。


5月のお茶会やパーティー等に宜しいのではないでしょうか。
この付下げは、むらたやがお薦めする一品です。涼しそうなお色におめでたい柄を
描いた重宝する一品です。
きもの むらたや
https://www.kimono-murataya.com/

TEL 0856-22-0095 (代表)
TEL 0856-22-0098 (ネット専用)
商品に関するお問い合わせは 、こちらまで